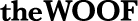皆さんこんにちは!読書犬・パグのぐりです。お元気ですか? 昨年3月からこちら、WOOFOO天国出張所にて仕事をしている僕ですが、毎年地上の冬は寒くて寒くてちょっと苦手だったんだけど、こちらは快適です~。
地上での飼い主Nさんによれば、「幼稚園や小学校では、胃腸炎、インフルエンザ、風邪と、冬の病気がはやり始めたよー(泣)」ということですが、皆さんもお気を付け下さいね。
アメリカの介助犬事情

昨年の年末スペシャルで、子ども向けの本を紹介した時に、『ぼくはチューズデー』という、アメリカの介助犬が主人公の写真絵本を読みました。この本を読んだ時から、アメリカ社会の介助犬への理解がとても進んでいることに興味をもっていたのですが、そしたら本屋でこんな本に出合ったんです。
『介助犬を育てる少女たち』(大塚敦子著 講談社 2012年)。この本は、アメリカ・カリフォルニアにある少女厚生施設・シエナで行われている「ドッグ・プログラム」を追ったノンフィクション。著者の大塚さんが、約2年をかけて取材し、まとめています。
このドッグ・プログラムは、心に傷をかかえ、非行や犯罪など、それぞれの理由から厚生施設へきた少女たちが、介助犬を育てるプログラムに参加することで、自己肯定感をたかめ、同時に介助犬の育成も進めるという画期的な試みです。そんなことできるの!?って読みはじめた当初は思ったんだけれど、読み終わってみるとそのプログラムのすばらしさを実感できる内容でした。
辛いバックグラウンドをもつ少女たち

この本の中では、3人の少女が登場します。エイミーは母子家庭で育っていたのですが、母親は仕事が忙しく、エイミーに目や心をかけることが難しかった。その結果、エイミーは10代から酒や麻薬に手を出し、何度も鑑別所に送られることに。一向に厚生しないエイミーに業を煮やした少年裁判所は、シエナにエイミーを送ります。
シエナに来たエイミーはそこでもある悪いことをしてしまうのですが、希望して入ったドッグ・プログラムのクラスで、自分の犬を任されることで、少しずつ変わっていくのです。
ティナは13歳で息子を出産。その後窃盗や喧嘩を繰り返したことで施設へ送られました。息子に会えない寂しさ、不法移民であった父親の国外追放、ティナの心にはいつも雲がかかっていました。そんなティナも介助犬候補犬のザイランを任せられることによって、少しずつ気持ちが前向きになっていきます。
ニコルはそれほど重大な罪をおかしたわけではないのですが、その家庭環境があまりにも不安定だったために、シエナに送られてきました。いつも自信のない彼女も、ドッグ・プログラムで少しずつ自分を肯定できるようになっていきます。
この3人の少女たちを支え、一緒に介助犬の育成にかかわっていたのは、なんと日本人女性。インストラクターの鋒山佐恵さん。「サエ」と呼ばれ、少女たちから慕われている彼女は、世界で唯一、犬学専門のバーゲン大学の学生で、シエナでのプログラムの責任者でもあります。年の近いサエをシエナの少女たちは慕い、時に叱られ、時に励まされながら、一緒に歩む様子は心が温かくなります。
犬は、人を信じている生き物です。だから、自分を訓練する少女が、たとえ過去に犯罪にかかわっていたとしても、そんなことは知らないし、関係なく彼女を信じ、一緒に歩もうとする。そうすると少女たちはどんな気持ちになるでしょうか。シエナに来るまで、家族の温かさを知らず、寂しさから窃盗や飲酒・薬物などに逃げていた彼女たち。自分を認めてほしいから、自分のほうを向いて欲しいからわざと悪さをする子も多いのです。自分のことを認めてもらえないと「私なんか、いたってしょうがないんだ」という投げやりな気持ちになってきます。
ですから彼女たちになんとかして自己肯定感、つまり自分がいていいんだ、という自信を持ってもらいたい。シエナに関わるスタッフは皆それを思っています。ドッグ・プログラムでは、犬は絶対の信頼を持って訓練士である少女に接する。すぐにコマンドを理解してできるわけではないけれど、根気強く続けることで、やがて犬に伝わり、できるようになる。そうすると私にもできる、という自信が生まれます。そしてその積み重ねの最後に、実際に障がいのある人へ、自分が育ててきた介助犬を渡すのですが、そこで「自分は人の役に立てた」という達成感を生むのです。
自分も人の役に立てるという自信

とても考えられたプログラムの内容に僕もびっくりしたよ。そして、このプログラムを成功させるために尽力しているスタッフの人たちの情熱にも頭がさがる。現実には、この3人の少女のように、プログラムを終えられる子たちばかりではないんだって。行きつ戻りつしながら、ちょっとずつ進んでいく。大変な根気のいる仕事だね。
でもニコルのこんな言葉に、このプログラムの尊さが現れています。
「わたし、犬の訓練をしているとき、誰かを助けるためにやっているというより、犬がわたしを助けてくれている、これはわたしのための訓練なんだ、という意識のほうが強かったの。それが、ザックやミリアムに出会って、その先がつながった気がする。癒しの連鎖、とでもいうのかな……自分の助けになることが、介助犬を必要とするほかの人たちを助けることにもつながっているんだとわかったの」(p.191)
今日もカリフォルニアの空の下で、社会に出て行こうとする少女たちが介助犬を育てているのでしょう。
アメリカの、介助犬への理解の深さ、育成のすそ野の広さを垣間見られる1冊。ぜひ読んでみてくださいね。
講談社
売り上げランキング: 565,738
Featured image credit josh / Flickr